Home > Ruby on Rails Archive
Ruby on Rails Archive
夏休みに開発合宿に参加してきました
- 2007-07-31 (Tue)
- Ruby on Rails
 さて、夏だ!夏休みだ!合宿だ!と言うことで7/30、31と、晴海グランドホテルで行われたNIFTY主催の開発合宿に参加してきました。
さて、夏だ!夏休みだ!合宿だ!と言うことで7/30、31と、晴海グランドホテルで行われたNIFTY主催の開発合宿に参加してきました。
仕事じゃないので、自分の会社は夏休みを取って個人的に参加です。これで夏も終わりか・・・
この合宿、NIFTYさんが中心ですが、色々な会社の人が参加していて、総勢20名と、かなりの人数でとなりました。
参加者には内緒のテーマがあり、それに沿って、全員がそれぞれ別々の物を作って、2日目の夕方から発表を行うという形で、進んでいきました。
私は、簡単に作れるシンプル目のサイトを作ろう考え、ひさびさに、2日間プログラムの事だけを考えて、ひたすらコーディングして2本の小さなサイトを、なんとか作り終えました。
微調整とか諸々をして、来週には公開予定です。他の方々も色々面白い物を作っていて、来週ぐらいには公開されていくと思うので、公開されしだい、このブログで紹介します。
いま合宿が終わってやっと家に帰ってきました。激しく疲れたけど、楽しかった。会社の仕事をしているとメールを見たり電話が来たりするけど、そういう中断が、いかに集中力を乱すかよく分かりました。でもこの勢いで毎日プログラムしてたら寿命が縮みそうw
今日はお休み
- 2007-07-14 (Sat)
- Ruby on Rails
毎日blog書こうと思ってたんだけど、今日はお休み。
色々溜まった個人的な仕事をこなす予定。
mooにシールが登場するらしい。
今までも友人にmasuidriveシールを作ってもらって、色々なモノに貼ってたんだけど、今度はもっと手軽に使えるなぁ。
QRコードにして、全部違うURLのシールとか。
続masuidrive的プロジェクトの方針
- 2007-07-14 (Sat)
- Ruby on Rails
オレンジニュースさん、textfile.orgさんにも取り上げてもらい、masuidrive的プロジェクトの方針が予想以上の反響を頂いてちょっとびっくりしてます。
この文章自体の前提が普通の会社の組織じゃないので、そのまま参考にはちょっとならないかもしれません。ただ自分の考えをプレゼンにするというのが、すこしでも普及してくれると嬉しいなと思ってます。プレゼン資料を作りつつ、脳内プレゼンをしていると、意外に抜けている自分に気がつくので。
この対象のプロジェクトメンバーは波長の合う人を社内公募などで募って、そもそもこれを受け入れて一緒にやっていける人を前提に考えています。なのでかなり上段から見たような文章になっていますw ウチの会社自体は、とがった会社ではないので他部署で適用することは、あまり考えてません。
私が個人でやってきた方法論が、どこまで組織で通用するのか、どこで行き詰まるのかを自分で楽しみにしてます。それを糧にもう少し一般化した方法論が書けないかなとも思っています。
Tracを重要視するのは、RSSリーダで新しい指示の確認ができるからです。プロジェクトメンバーには、情報収集の意味も含めて全員RSSリーダを常用してもらおうと思っているので。
自分でも社内の他の部署との仕事もあり、情報を一元管理できないと、すでに追えない状況になっています。他部署の方に、「私への指示はTrac経由でのみ受け付けています」とはお願いできないので、まずは自分の部署からという感じです。
もぎゃさんからリクエストの「subversionでのファイル管理方法」も含めて、もう少し細かい部分も書いていきます。この連休ぐらいには。
プロジェクトの始まりはTracから
- 2007-07-12 (Thu)
- Ruby on Rails
そんなわけで、プロジェクトの始まりはTracから。これがないと仕事が始まりません。
Tracが一番良いわけでも無いんだけど、日本語マニュアルがあるところと、ユーザが多いことから、subversionとの連携スクリプトなどが多数公開されているところが、選択理由です。
Railsベースでも複数、プロジェクト管理ソフトが出てきているので、どれか良い物に育ってくれると嬉しいなと思っています。
さて、tracのインストール方法はwebで沢山見つかるので、それを参考にインストール。
Tracは初期設定でも十分使いやすいんですが、チケット登録で担当者をドロップダウンリストにするために設定を変更します。
tracの設定ファイル conf/trac.iniの下記の項目を変更してください。
[trac] default_charset = utf-8 # 文字コードはUTF-8で [ticket] restrict_owner = true # 担当者をドロップダウンリストにする
ユーザ登録は、.htpasswdにユーザを登録後、下記のコマンドを実行して権限を与えます。
trac-admin ./ permission add アカウント名 TRAC_ADMIN
そのあと、このユーザにはログインしてもらい、画面の右上「ユーザ設定」からメールアドレスを登録してもらいます。これを登録して貰わないとチケット登録画面の担当者として選択できません。
あとは、コンポーネントと優先度を変更します。まずは優先度を日本語にします。
trac-admin ./ priority change blocker 今すぐやる trac-admin ./ priority change critical 急いでやる trac-admin ./ priority change major 普通 trac-admin ./ priority change minor あとでもいい trac-admin ./ priority change trivial そのうちやる
次にコンポーネントを変更します。
trac-admin ./ component rename component1 コード trac-admin ./ component rename component2 仕様書 trac-admin ./ component add 会議 somebody
最後にチケットの分類を変更します。
trac-admin ./ ticket_type change defect 不具合 trac-admin ./ ticket_type change enhancement 機能拡張 trac-admin ./ ticket_type change task タスク
これで完了。もちろん、これもコマンド化してsubversionに入れておきましょう。
あと、メンバーの未処理チケットを簡単に確認できるようにメンバー分だけレポートを登録しておきます。
下記のレポートSQLを「メンバー名の未処理チケット」というタイトルで保存しておくと、メンバーの作業進行具合がわかって良い感じです。
SELECT p.value AS __color__,
(CASE status WHEN 'assigned' THEN 'Assigned' ELSE 'Owned' END) AS __group__,
id AS ticket, summary, component, version, milestone,
t.type AS type, priority, time AS created,
changetime AS _changetime, description AS _description,
reporter AS _reporter
FROM ticket t, enum p
WHERE t.status IN ('new', 'assigned', 'reopened')
AND p.name = t.priority AND p.type = 'priority' AND owner = 'メンバー名'
ORDER BY (status = 'assigned') DESC, p.value, milestone, t.type, time
とりあえずは、ここまで。明日はsubversionとの連携スクリプトですw
masuidrive的プロジェクトの方針
- 2007-07-11 (Wed)
- Ruby on Rails
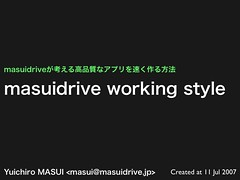 初めて会社員になって早3ヶ月。会社の仕組みもやっと分かってきたし、そろそろ本格的に開発プロジェクトも動いて行くということで、今後、社内で私と一緒に開発して行く人に、「私がどういう考えで仕事を進めていきたいか」という事を知ってもらうためのプレゼンを作ってみました。(今のところ一人だけど)
初めて会社員になって早3ヶ月。会社の仕組みもやっと分かってきたし、そろそろ本格的に開発プロジェクトも動いて行くということで、今後、社内で私と一緒に開発して行く人に、「私がどういう考えで仕事を進めていきたいか」という事を知ってもらうためのプレゼンを作ってみました。(今のところ一人だけど)
NIFTYさんと仕事した時も、作業に入る前に「今までどうやって遠隔地で仕事を進めてきたのか」をプレゼンしていました。特に初めて仕事をする場合、「今まで自分はどういう風に仕事をしてきて、この仕事はどういう風に勧めていきたいか」を明確にしておくと、スムーズに仕事を進めることができます。
仕事、特にその上でのコミュニケーションをうまく進めていくためには、信頼と共通認識が必要だと思ってます。信頼は当たり前の話ですが、開発を進める上での共通認識についてはあまり重要視されることが無い気がしています。
仕事をする上ではコミュニケーションが欠かせませんが、特に社内のコミュニケーションは口頭による指示が中心になると思います。何か指示をするにしても、「なぜ今その指示をするのか」「これをすると何のためになるのか」と言った背景が全ての指示で語られることはありません。実際、すべてを説明している時間は無いはずです。
しかし、理由や目的の伝わらない指示は、なかなか思うとおりに実行されません。ここにメンバー間でしっかりとした共通認識があれば「この指示はこの部分に必要なんだろうな」と目的を推測したり、「ここは私ならこう思うから、違う理由を聞いてみよう」などの、アクションが取りやすくなると思います。
そこで、せっかく個人では無く、会社員として仕事をするので、この共通認識の部分をプレゼンにまとめて、これを基盤に仕事の方針を決めていきたいと思います。とは言っても、初めてこういう事をやるので、まだまだ全然なダメダメな資料です。しかし明示することによって、おかしいところも気がつきやすく、見直しもしやすくなるだろうと思って、ブログに公開することにしました。
オンラインとPDFで公開しているので、もし良ければご覧下さい。
一緒に仕事をする人には、この資料を読んで「masuidriveなら、こういう風に考えるだろうから、こうしておこう」とか「この指示は、こういう考えでだしたんじゃないかな」と考えて貰えるようになれば大成功だと思っています。
なにせ会社員経験が浅いので、一般的な会社の仕事の進め方が分からず、この資料のどこに違和感を感じるか、実行するのに何が難しいのか、もっと良い方法はどういう事があるのか、など分からない事だらけです。
もしこのプレゼン資料をみたら、何かコメントを残して貰えると嬉しいです。ぜひお気軽によろしくお願いします。
JRubyを中心に活躍されている、大場 光一郎さん <koichiro@meadowy.org>には、資料作成とブログの校正でご協力いただきました。この場を借りてお礼をさせていただきます。
新しいmoo card届きました & 営業に使う小ネタ
- 2007-07-10 (Tue)
- Ruby on Rails
 Flickrとかから簡単に小さい名刺を作れるサービスmoo cardが届きました。今回は2回目の注文。
Flickrとかから簡単に小さい名刺を作れるサービスmoo cardが届きました。今回は2回目の注文。
1セットで100枚なので、もうそんなに配ったんですね。
この名刺の面白いのは、片面が写真な所と、その写真を100枚全部違う物が指定できるところ。
自分のFlickrに入れてある物を選ぶのであれば、改めてアップする必要もないので、名刺に使いたい写真を選ぶだけ。
それでも、いつもくだらない写真ばかり取ってるので、名刺に使えそうなのは30枚程度。100枚に満たない場合は、適当に複数枚ずつ刷ってくれる模様。だから今回は大体1写真に付き3枚ずつぐらいあるはず。
主に、OSS関係とかで遊ぶ時用の名刺なんだけど、仕事の営業でも会社の名刺と併用で使ったりしています。
 ちょっと面白さを出すために、moo cardを全部裏返して、ババ抜きの様にして相手に見せ、「これ全部、違う写真が印刷されている名刺なんて一枚引いてみてください」という感じで1枚引いて貰います。
ちょっと面白さを出すために、moo cardを全部裏返して、ババ抜きの様にして相手に見せ、「これ全部、違う写真が印刷されている名刺なんて一枚引いてみてください」という感じで1枚引いて貰います。
全部、自分で撮った写真なので、「これはニセコで開発合宿した写真」とか「DHHと一緒の写真」とか「これウチの車。走るの大好きなんですよ」とか色々エピソードがあるので、それを会話のきっかけにする為に使っています。
実は車関係の会社に行くときは車とか旅の写真ばかりを、開発系の会社に行くときは机の様子や開発合宿の風景を中心に名刺入れに入れるようにして、話を作りやすいようにしてたりするんですがw
名刺のサイズが小さいので、携帯カメラでも十分な解像度(640×480程度)な所も手軽で良い感じです。
もし、人とちょっと変わった名刺を持ちたい場合。ちょっと覚えて貰いたい場合など、moo cardを試してみてはどうでしょう。イギリスの会社ですが、送料込み$25で1週間ちょっと届きます。
p.s
そろそろ、blogの更新もマメにやろうかなと思っていますので、見ていただいている人は、ぜひRSSリーダにご登録を。
RejectKaigi2007のスライドアップしました
- 2007-06-13 (Wed)
- Ruby on Rails
RubyKaigi2007のRejectKaigiで、風呂グラマーの話しをしてきました。
元々、mashfeed.comでpraggerにケンカを売るつもりだったんですが、風呂グラマーの方がウケそうだったので、ぎりぎりにスライド作り直しちゃいました。いや150秒とはいえ、練習を一度もしないのでつらかったー。
[RubyKaigi2007速報] JRuby 1.0 Released!
- 2007-06-09 (Sat)
- Ruby on Rails
JRuby 1.0の正式版がリリースされてた模様。
公式ページのニュースにも載ってないし・・・。
よくみたら、Downloadからダウンロードできるみたい。
早速試してみないと。
WordPressに乗り換えました
- 2007-01-30 (Tue)
- photoshare | Ruby on Rails
最近、あまりにSpamがひどいので、ブログをWordPressに乗り換えました。
Typoだとアンチスパムが弱かったり、コメントを消す動作が結構めんどうだったので、さっくりと乗り換えることに。
なお、過去のコンテンツは、そのまま残してあります。
前のトップページは、ここにありますので、古い情報を探しに来た方はそちらからどうぞ。
Home > Ruby on Rails Archive